生徒たちのレポート(25春・津和野共存病院)

2025年3月29日(土)から4月5日(土)にかけて津和野共存病院(島根県)で医療体験学習が行われ、高校生4人と医学生メンター1人が参加しました。
- Msさん(東京都立西高校2年)
粘り強さに自信がありコロナ禍ではルービックキューブを極めた - Krさん(千葉県・市川高校1年)
中学時代、数か月にわたり入院したのをきっかけに医師を目指すようになった - Mhさん(東京都・鷗友学園女子高校1年)
医師か看護師か進路選択で悩んでいる - Kkさん(東京都・渋谷教育学園渋谷高校1年)
「知らない力」が自分の一番の強みだという行動派 - Cさん(筑波大学医学群医学類4年)
【医学生メンター】TtFの活動をサポートしている学生の一人
それぞれ何を経験し学んだのか──生徒たちの声を紹介します!
医療体験に参加しようと思ったきっかけを教えてください

家族の病気や愛犬の死、また私自身が患者として医療に支えられている経験から、医師という職業が人の命に寄り添い、希望を与える存在であることを実感しました。将来は病気に苦しむ人の負担を軽減し、より良い治療を提供できる医師になりたいです。
臨床医として患者に寄り添う道と、研究者として病気の克服に挑む道のどちらにも関心があります。この医療体験では地域医療の実態を学んで、医師としての理想像が大まかに定まればよいなと思いました。

地方の医師がどのように患者さんと向き合っているのかを学びたいという大きな目標があります。私が暮らす地域では周りに大きな総合病院があり、アクセスもよく誰もが医療を受けられる環境が整っています。でも、地方では医療を受けたくても交通手段が限られ、緊急を要することがあっても治療をすぐに受けられないことが問題になっていること知りました。
この問題を踏まえて、最先端の高度過疎地域の医療従事者がどのように地域の住民と関わり、命と健康を支えているのかを学びたいと思いました。

将来、産婦人科医として地域医療に貢献したいという夢があります。でも、その夢は漠然としていて、本当に自分のやりたいことなのかと問われると、正直まだ分かりません。「なぜ医師になりたいのか」「医師として何がしたいのか、どう医療に携わりたいのか」を考えるうえで、この医療体験での学びを生かしたいと思いました。
私は人とのコミュニケーションが得意でないと自覚していますが、医師にとって患者さんとの対話は不可欠です。入院患者様を担当する医療体験で自分のベストを尽くし、弱点を克服するきっかけにしたいという目標もありました。

大好きな祖父を亡くしたことがきっかけに、一人でも多くの命を救いたい、支えたいという思いが芽生えました。そこで高1の夏、老人ホームで数回ボランティアをしたのですが、認知症や身体の不自由な方など多様な症状のお年寄りがいて、接し方に苦労しました。今回の地域医療体験では5日間にわたり患者さまを担当させていただけるので、「寄り添う」ことを経験したいと思いました。
また、現代の最先端医療をもってしても救えない命はあります。医師を志すにあたり、この体験を通じて超高齢化社会における医療現場の実態について学びたいという気持ちがありました。

津和野共存病院での医療体験はどうでしたか?

「過疎化が進む地域に住む人はかわいそう」という考えは間違っているということに気づきました。多少の不便はあったとしても、多くの人は津和野への愛と誇りを持って暮らしていました。東京に帰って満員電車で身動きが取れないでいると、津和野の記憶がよみがえります。「ああ、本当にいいところだった」なと。過疎地の医療も、予想していたほど困難な状況に追いやられているとは感じず、地域にマッチした病院だと思いました。
正直、今回の医療体験で「自分に医師は無理だ」と諦めてしまうような結果になったらどうしようと不安でした。でも、そんな不安は杞憂でした。医師になる決意が固まりました。医師という職業をいい意味で身近に感じ、人間らしい姿を見ることができて安心したからです。

人口減少が深刻な津和野町にはバスが1日一便しかなく、病院に行くのに1日かかってしまう医療過疎地域があります。その地域の人々の健康と命を守るため、津和野共存病院の医師は自ら無医地区を訪れ、公民館で多くの患者さんを診ていました。この巡回診療に同行して学んだのは、医療とは治すことが全てでないということ。人々は持病と向き合いながら、病気が悪化しないように医療を受け、普通に暮らしているのです。
こうして地域医療にどっぷりつかりつつ、5日間で最も考え方が変わったのは「死」の受け止めかたでした。死は避けられないと頭では理解できても、私は患者さんの死が怖かった。医師を目指すうえで、果たして自分は死に向き合えるのかが一番の課題でした。そして、5日間の体験のなかでお看取りの現場に立ち会わせていただきました。ご家族の方々は医師に「色々先生に助けていただきました。ありがとうございました」と伝え、死を穏やかに受け入れいてるように見えました。その空間に悲しみはあっても恐怖はなく、医療現場の現実を実感した瞬間でした。
津和野町では医師をはじめ、多職種の方々が患者さんの最期をサポートしていると学びました。最期まで患者さんを診ることで、家族だけでなく医療者にとっても死の受け入れ方は変わると感じました。私は患者さんの最期まで向き合える医師になりたいという決意ができました。この決意を心に留めて医師を目指します。

今回の医療体験で、地域医療とは「地域に根ざし、みんなで一人の住民に寄り添うこと」だと捉えるようになりました。まず「地域に根ざす」とは地域における「その人らしさ」を尊重すること。例えば、畑仕事による膝の痛みを訴えている方の場合、「畑はやめましょう」と諭すのではなく、「できる範囲で続けられるよう治療してリハビリをしましょう」と励まします。畑仕事が好きというその人らしさを尊重するのです。
次に『みんなで』というのは多職種連携です。想像していた以上に多くの職種の方々が一人の患者さんを守っていました。朝のカンファレンスではそれぞれの立場からの意見を交換していました。
私が忘れられないのは、院外でも地域の人とつながり包括的に患者さんに対応していることでした。その様子を目の当たりにしたのは、認知症がある男性宅に訪問看護でお伺いしたときのこと。男性は毎回のように約束の時間を忘れて外出してしまい、私が同行したときも不在。すると、看護師さんが「外出するときは郵便局に寄る」と言うので行ってみました。私たちの車が郵便局前に止まった瞬間、局員が察したような笑顔を浮かべて「買い物に行かれましたよ」と教えてくれたのです。「こんなところでも連携しているのか!」と、もう本当に驚きました。
帰京後に振り返っても、私の住んでいる街で看護師さんと郵便局員が情報共有するようなことはまずないだろうと思いました。まさに、「共助」のあり方を学ぶことができたと思っています。

医療における「寄り添い」とは何か――。津和野共存病院で5日間を過ごしてたどりついたのは、「患者さんの小さな願望を汲み取る」というものでした。私が担当させていただいたのは、慢性心不全で入院して間もない男性の患者さん。介護度のレベル変更が認められるまで退院が難しいとされており、自宅に戻ることを一刻も早く叶えてあげることが「寄り添う」ことになってしまうと、手も足も出なくなってしまうと感じました。
加えて患者さんは食べ物に好き嫌いがなく、いつでも電話に出てくださる奥様がいたため、入院生活を特別に憂鬱なものに感じられている様子はありませんでした。そこで、入院によって出来なくなってしまったことを叶えるため私にできることを探りはじめました。ベッドサイドで話すなか桜に度々興味を示すことに気がつき、そこから「お花見」の案を考え付きました。30分程度でしたが、患者さんを乗せた車椅子を押して津和野川沿いの桜並木へ。「一生の思い出になった」と喜んでくださったことは決して忘れられません。小さな幸せを提供することこそが「寄り添い」の姿であると感じました。
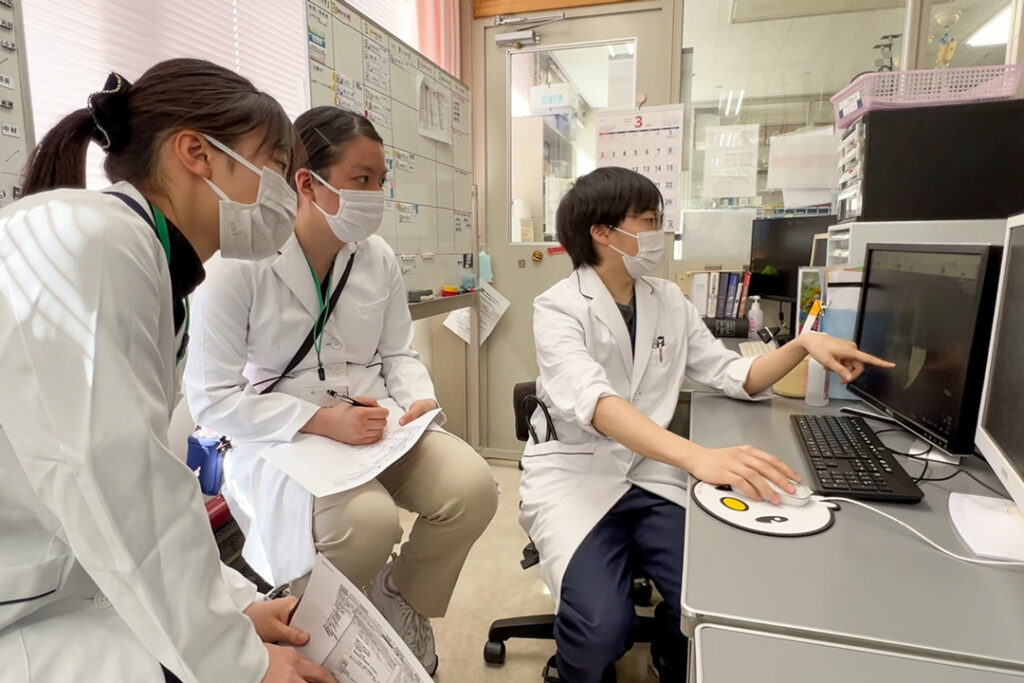
患者さんとのエピソードで印象に残っていることは?

私が担当した患者さんは100 歳の女性。本当に気持ちが優しくて、起居や食事など生活をする上で必要な基本的な動作ができる方でした。でも、すでに幸せな患者さんに対して、自分にが何ができるのかわからず戸惑いました。亡くなったご主人の話になったとき、患者さんが涙を流されたので、私は彼女を悲しい気持ちにしてしまったという罪悪感でいっぱいになりました。
このことについて振り返りMTGで明かすと、先生は「ただ話すだけでも患者さんの幸せにつながります」と語りました。「共に過ごす」ことがいかに大事なのかに気づいた瞬間でした。試行錯誤の繰り返しでしたが、最終日に「いい子に担当してもらった」と患者さんに言ってもらえて、どれだけ嬉しかったか。患者さんとの出会いは一生忘れません。

私はこの体験を通して悔やむことがあります。それは医療体験2日目、担当患者さんの退院前訪問で一緒に自宅にお伺いした後のことです。病院に戻り「患者さんを励まそう」と思ったのに、病室の前で足が止まってしまいました。なぜ、躊躇してしまったのか――。
患者さんは筋疾患の難病がある方で、今回は骨折治療のために入院。退院後は自宅で暮らすことを強く望んでいました。久しぶりに自宅に戻った患者さんですが、長期入院で筋力が低下し、寝室から隣の部屋に自力で移動することができません。このままでは自宅に戻ることはできず施設に入所するしかないのですが、本人は施設には否定的です。
私も入院で体力と筋力が落ちて気持ちが沈んだ経験があり、その心境が分かるからこそ患者さんにかけられる言葉があると思いました。でも、どんな言葉をかけていいのか分からず怖くなり、足が止まってしまったのです。担当の理学療法士さんによると、現在の状態で自宅に戻ると怪我をしかねず、怪我で身体を動かせなくなると筋疾患の進行が早まり、寝たきりになるリスクもあるとのこと。患者さんに寄り添うことは決して簡単ではなく、むしろ難しいことなのだという現実を突き付けられました。
最後の2日間は患者さんに病気の悩みを忘れてもらい、ストレスを和らげられる時間を作ることに専念しました。患者さんの車椅子を押して一緒に院外でお花見に出かけました。満開の桜の下、患者さんの楽しそうな声は今でも心に残っています。この5日間で私が患者さんにできたことは本当にわずかです。それでも患者さんと過ごした時間には学びがあり、悲しみがあり、楽しいことがあったかけがえのない時間でした。

深い縟瘡(じょくそう、床ずれのこと)ができている70代の女性を担当したことで、寄り添いには二つの要素があると考えるようになりました。
一つ目は痛みを理解すること。縟瘡の処置中「痛い、痛い」と泣く女性を目の前にして、「患者さんのためにも何もできない」という無力感を覚えました。その一方で、100%ではないものの女性の痛みを理解できると感じました。それは、自宅に帰りたいと願いつつ退院が叶わず、精神的に落ち込んでいることを主治医の先生や担当看護師、社会福祉士の方々からお伺いしていたからです。痛いという訴えがより強く感じられ、その瞬間「物理的な痛み」と「精神的な苦痛」がつながりました。全人的な痛みの理解が患者さんに寄り添うためには欠かせないと思えました。
二つ目は、その人の目線に立つこと。女性は気持ちが沈んでいるせいか食が進みません。そこで管理栄養士さんと相談すると、朝食が白米からパンに変わりました。ですが、感情をあまり表に出さない方のため、パン食についての反応を確認できませんでした。果たしてメニュー変更は患者さんのためになったのか、ただの自己満足にすぎなかったのか。本当に悩みました。相手の目線に立ち、気持ちを理解することの難しさを今までの人生で一番強く感じました。

5日間のプログラムで得た気づきはたくさんあります。そのうちの一つは、「機会は自ら作り出すもの」ということ。先生方が組んだスケジュールを軸に院内外で医療の現場に密着しますが、予定の入っていない時間が多くありました。この「空き時間」の使い方が高校生自身に委ねられていたことは、積極的に行動することを促していたと感じました。
Touch the Futureの医療体験の特色は「高校生が入院患者さんを担当すること」ですが、この「空き時間」を的確に利用する必要があると感じました。患者さんと過ごす時間の量にとらわれると、話題が尽きて困ってしまいます。行動するにしても何が目標で、何が手段で何をしたいのかを明確にしないと、忙しい医療スタッフのサポートを得るのは難しいと感じました。
また、 「会話をするだけで楽しい」と言ってくださる担当患者さんに対して自分がそばにいてあげること以上の何かを与えたいという発想に一人で至ることができませんでした。ですが、医師や看護師、医学生メンターからのアドバイスがあり、一緒に参加した生徒3人から学ぶことが多々ありました。現に、3人は料理本を患者さんに読み聞かせたり、長年会えていない家族との面談を作ろうとしたりと試行錯誤をしていました。そんな仲間たちに感化され、私も「会話」を手段に変え、「入院によってできないことを実現する」という目標を立てることができました。


医師や医療スタッフとのエピソードで印象に残っていることは?

患者さんに寄り添うとは何かを考えさせられた5日間でした。まず分かったのは、医師は患者さんといられる時間が少ないということ。限られた時間の中でどう患者さんに寄り添うかが大事なのであって、そのために多職種が分業して連携しているのだと分かりました。まさにチーム医療です。また、濱崎先生は「オンとオフの切り替えが大切」「メリハリをつけて患者さんと接します」とおっしゃっていてすごく納得しました。
看護師やリハビリ療法士へのイメージも変わりましたが、共通していたのは「愛」です。患者さんが車椅子で紙袋を足で挟んで進みにくそうにしていたので、私は紙袋を持ってあげようとしました。でも看護師さんは「あるきんしゃい」と言って患者さんに紙袋を持たせて手すりをつたって歩くように促していました。「ただ優しいだけじゃだめだよな」と思い、そこに愛を感じました。
入院患者さんと一緒に自宅の状況をチェックする退院前訪問にも愛がありました。社会福祉士さんは「ドライブしましょう」と宣言すると、車が向かったのは街を一望できる太鼓谷稲荷神社。桜と街を患者さんが眺められるようにしたのです。患者さんは「何十年ぶりの神社」と嬉しそうでした。それぞれのフィールドに「患者さんをより幸福にしたい」という愛があり、これが寄り添うことなのかと思いました。

担当患者さんが退院して自宅で暮らせるようにするには、どうしたらいいのか。筋疾患の知識がなかった私は、院内を駆けずり回って多くの方々に話を聞き、アドバイスをいただきました。主治医の先生はもちろん、医局の他の医師たちや理学療法士、社会福祉士の方々。みんな忙しいなか時間を作ってくださり感謝の気持ちで一杯です。
こうして大勢のスタッフの時間をいただいたのですが、患者さんの筋力の回復は医学的には難しいこと、cureには限界があるということを学びました。ただ、医療にはもう一つcareがあります。私はcareの存在を分かっていながら、どこかに置いてきてしまっていたことに気づきました。この大切な気づきは、やはり多職種の方々の助けがあったから得られました。
また、担当患者さんのことを心配して思い詰めていたところ、飯島先生に「患者さんを思うことは大切だけれども、バーンアウトしてはいけないよ」と声をかけてくれました。この言葉は医療体験中、私の心の支えになりました。医療のバーンアウト(燃え尽き症候群)とは、医療従事者が長期間にわたるストレスや過労によって、仕事への意欲や熱意を失い、心が折れてしまう状態のこと。飯島先生だけでなく、社会福祉士の方などから温かい言葉をかけてもらい、それによって医療体験をやりきることができました。

救急外来、予約外来、診療所での診察を見学して感じたのは、どれも一回の診察時間が長く、とても丁寧ということ。特に、医師が「他に心配なことはないですか」「今畑はどんな感じですか」などと軽い雑談もはさみながら患者さんの様子について細かく聞いていたのが印象に残っています。私がふだん行く近くの病院で、ここまで丁寧に診察されることはまずありません。患者さんの生活に密着した丁寧な診療があるべき姿だろうと思いますが、都心の病院は患者さんの数が多くてじっくり診察というわけにいかないのかもしれません…
看護師さんのきめ細かいcareにも目を見張りました。最終日の訪問看護でお伺いした70代女性は入退院を繰り返していることに引け目があるらしく、「色々な人に迷惑をかけてばかり」と後ろ向き。そんな女性に看護師さんは「うんうん」と相槌を打って共感したうえで、「病気っていうのは誰のせいでもないんです、だから自分を責めないで」と優しく声をかけていました。
その看護師さんに一番大切にしていることを教えてください聞いたところ、「一言で言うなら『愛』ですね」と答えてくれました。訪問看護で女性に対して見せたあの優しさと寄り添いの精神は「愛」があるからこそ生まれたものだったのだと気づきました。将来は「愛」を忘れない医療者になりたいです。

「傾聴」という名の医療が印象に残っています。2日目に日原診療所の外来見学に同行した際、隣にある通所リハビリの施設を訪問しました。帰り際に理学療法士の中村祐哉さんがアドバイスしてくれたのは傾聴の大切さ。中村さん曰く「話を遮らずに不安や願望を聞いて共感すると、患者さんの状態や気持ちを正確に把握できます」。話してもらわないと患者さんが望む環境を提供できないし、時には自分を曝け出して相手の話を聞きだすことも必要だとと教えてくれました。
また、リハビリに通っているお年寄りは「入院中に辛かったのは病気以上に、人とふだん通りに関われなくなったこと」「病室のカーテンと天井だけを見て過ごしていると気が狂ったような気持ちになった」と話していました。現に私の担当患者さんは毎日のように奥様と電話でやりとりしていましたし、私と話したことをカレンダーに書くほど「会話」に大きな喜びを見出していました。
これは患者さんに限らず、健康体の人にも言えることかもしれません。私自身も、転んで外傷を負う回数よりも、心が不安定になって気分が落ち込むことの方が数えきれないほど多い。その際に何よりも求めるものは、共感してくれる存在です。「傾聴」することがいかに有効で医療に欠かせないかを学べました。


医療体験を終えて、改めて目標を聞かせてください

以前は、研究分野で一気に多くの人の役に立ちたいと思っていましたが、今回の医療体験を通して、人と顔を合わせて医療するという形も素敵だなと思いました。地域医療の魅力にも気づき、選択肢が増えました。
今の私には幾つかの目標があります。
一つ:医療者の立場と患者さんの立場両方の視点が持つこと
二つ:医師としてやるべきことを超えた配慮をすること
三つ:患者さんにとってのベストを探し続けること
四つ:いつまでも一人の人間としての心を忘れないこと
五つ:初心を忘れないこと
東京に帰ってみると、街で見る高齢者は津和野で会った高齢者より随分若い人ばかり。1人で歩ける高齢者はかなり健康な状態で、家の中や病院には寝たきりの方がいる、という視点を持つようになりました。自分が見えていた世界は狭かったと思います。きっと今もまだ狭いはず。これから色々なことを学んで見える世界を広げていきたいです。

自分が入院したときのストレスと不安を和らげてくれたのは、親身になって接してくれた主治医でした。その際、医師は病気を治療するだけでなく、コミュニケーションによって心のケアもできる存在なのだと知り、私も患者に寄り添える医師になりたいと思ったのです。今回の医療体験に参加して、その思いは強固なものとなりました。
医療体験に参加して良かったのは、寄り添うとはただ患者さんの話を聞いて、患者さんの希望に沿った医療を行うことではないのだと分かったこと。正解のないことかもしれないとも感じました。今の未熟な私では正解にたどり着けると思えませんが、それを探しつづける医師になりたいです。

担当患者さんの目線に立つことができず、考えの甘さを自省した5日間でした。自分にできることは何かを悩み、ふと思ったのは「ご主人と会えば元気が出るかもしれない」ということ。コロナ対策のため病院は1月から面会が禁止されていたのです。主治医の先生らと相談したところ、総合的な判断のもと医療体験最終日に面会が実現、ご主人と会った患者さんは笑顔を浮かべました。面会は私がセッティングしたものではありませんが、社会福祉士さんは「あなたが口火を切ったのよ」と言ってくれました。医学的知識がない高校生でも出来ることはあると感じた瞬間でした。10分の面会でしたが一生忘れない10分。寄り添う精神を持ち続けようと誓いました。
医師か看護師か、どの道を目指すべきなのかはこの1週間では決められませんでした。それでも「地域に根ざした寄り添いの医療を提供する医療者になる」「医療者として地方でも女性が出産しやすい環境をつくる」という明確な目標ができました。津和野共存病院でお世話になった医療者の方々の姿を思い浮かべながら、これから自分の進路を決めます。

誰かを直接助けたいという思いは変わらないものの、人としての心を忘れないお医者さんになりたいと感じるようになりました。今でも思い出すのは、「カルテを見る前に人を見る」という医学生メンターの言葉です。病気を患っていても患者さんは一人の人間であり、愛する家族がいて、誇りに思うことがあり、楽しいと感じる趣味があるのだと気づかされました。
病気を治してあげられないとなったとき、「患者」という視点のみで見てしまうと「この病気は治らないから諦めるしかない」という考え方に陥ると思います。ですが、一人の人間として見れば「少しでも愛する奥様のそばにいられるよう、リハビリに集中してみよう」「ケアマネジャーさんと相談して受けられる介護サービスを増やしてあげよう」など、幸せを提供できる医師になれると感じます。




